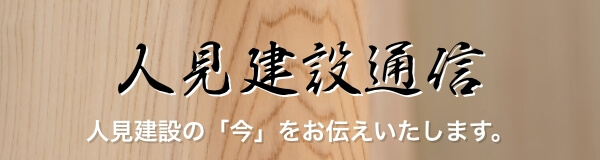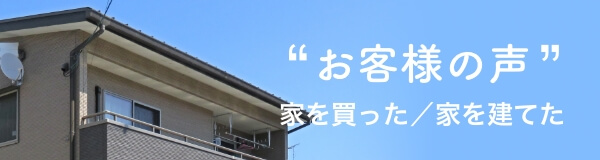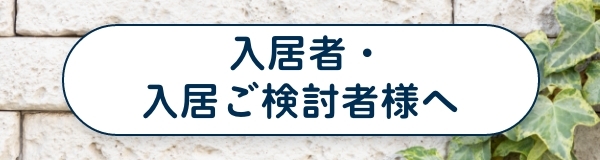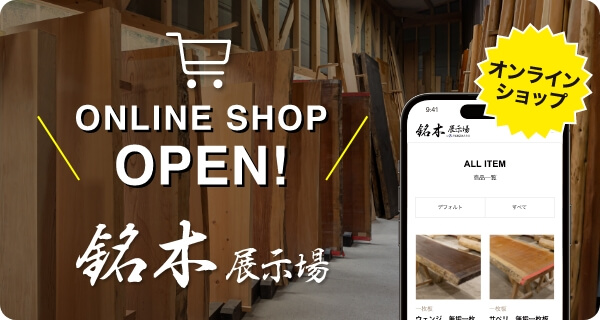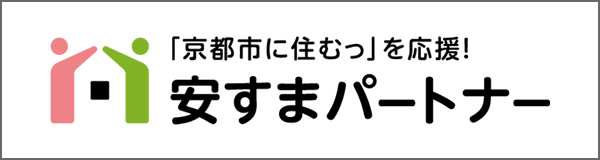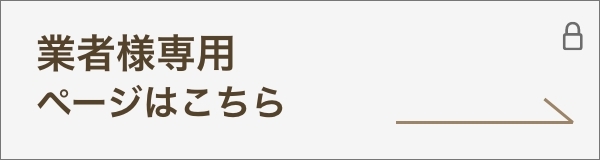相談役コラム
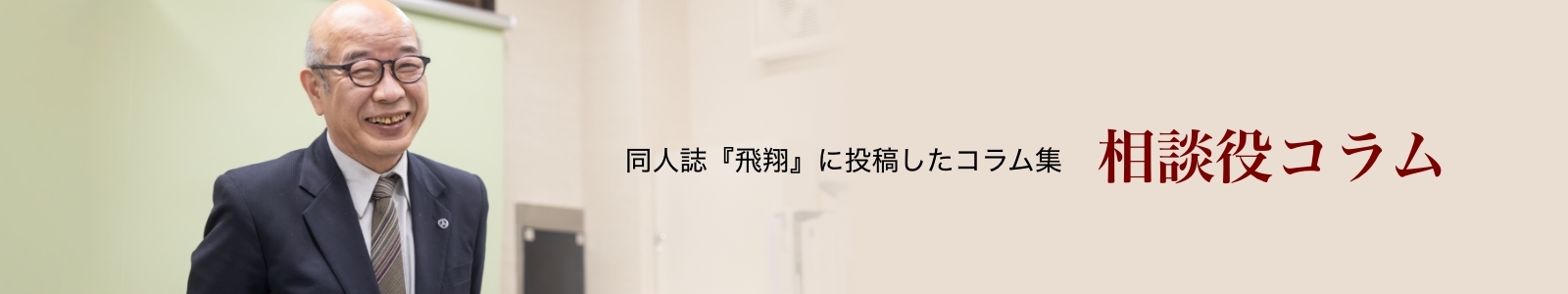
9.22025
木材市(いち)
戦後の全国緑化政策で植林された杉や桧は、家電や自動車の輸出大企業の見返りに、木材関税撤廃で国内に外材が押し寄せ、内地材の価格が暴落して日本の林業は衰退し山は荒れた。
数十年育った杉や桧の原木価格が、一本500円にしかならない時代が永らく続いてきたが、建築工事で使用される国産材のシェアが外材を押さえてやっと50%を越えたと、報道で知った。
十数年通っている「市」が創立30周年を迎え、記念市が開催されるので久しぶりに社員を連れて参加した。
開式の理事長の挨拶からも、市売りを手探りでやってきたこの施設の発展を、開設から勤めておられる馴染みの数名の顔がまぶしかった。
岐阜県恵那市にあるこの施設は1994年、国産材の流通合理化と木造住宅の建設促進を図るために、林野庁の「国産材産地体制整備事業」の一環として国、岐阜県、恵那市の協力によって、協同組合東濃地域木材流通センター、通称「木キーポイント」として設立された。
東濃桧など国産材の製材所と「工務店さん・大工さん・設計士さん・材木屋さん」などの技術者と施主様の3者を、情報と流通で結ぶ木キーポイントとなることを目指して取り組んでいる。
中央道真ん中のこの地が選ばれたのは、関東や関西と等距離にあり、私も高速を走って2時間半で通える。東濃桧の産地で40ケ所の製材工場から集めた構造材(管柱、通柱、土台、桁材)や造作材(鴨居、敷居、床材、羽目板)を中心にしているほか、隣県の木曽桧、椹材、三河杉、秋田、吉野、四国、九州からの木材も取り扱っている。
昔は、木材市は鑑札を持っている材木商でなければ、参加出来なかったが国産材の流通合理化を図る木キーポイントのような組織は今、全国にいくつかある。
市売りは毎月2回と記念市は年4回開催され、実際の材を見て、触れて製材業者や委託先業者から出された材の競り市が行なわれる。材には参考価格(委託業者の)が表示
されているが、競りによって上下する。
落札された価格は、出荷業者が市の手数料を払うので、落札した価格で購入することが出来、合理化された流通システムによって、市価の2~3割ほど安く購入出来ますが、誰も手を上げなければ、どんどん下がっていき、参考価格の半値以下になることもある。それも競り子の判断で落札者が無い場合は、次回に持ち越される。
私の自宅の玄関ポーチ柱(長さ3m、末口3寸の変木)は、連れ合いが5万の参考価格を一万以下で競り落とし、磨き加工代にもならない価格で購入した。
10年ほど前、お寺の施設を請負った時は、木キーポイントさんに桧4m五寸角管柱をはじめ大きな材を各地から調達していただき大変助かった。
数年前コロナ過の木材品薄、価格暴騰の時は、皆が競り子の前に集まって、始まると一斉に手を上げるものだから、各人一梱包ずつにして下さいと取り合いになった。今はだいぶ落ちついて来たが、工法が変わり、手間の架かる材は敬遠され、値段が付かないものがある。この前も杉下地材2m小幅板が落ちなかった。板を並べる手間を考えると3×6合板で手っ取りばやく仕事がしたいのだ。
私の自宅は合板を一切使用しなかったので、杉の下地板を木キーポイントで大量に購入した。杉板厚み30㎜の断熱性能は合板の比ではないと思える。洋間はその上に15㎜の桧フローリングを張って、45㎜厚にしたので、床下断熱材は入れなかった。
京都北山の宗教施設の改修現場に行ったとき、鬱蒼とした山の中の施設で、冬は零下10度を下回り、雪が溶けない苛酷な条件で、廊下や縁の床板は高級な松合板フローリングが張ってあるのだが、みんなぶかぶかしている。「湿気が都会とは違うので、何ともなりません」と、おっしゃられた。「無垢のフローリングならこのようなことにはなりません」と指摘しておいた。合板は所詮接着剤ではぎ合わせてあるのでいつかは剥がれていくと思う。